大型トラック市場 規模・シェア分析:成長トレンドと予測(2025年~2030年)
大型トラック市場レポートは、積載量タイプ(10トンから15トン、15トン超)、クラス(クラス7、クラス8)、推進方式(ディーゼル、バッテリー電気、その他)、用途(建設・鉱業、その他)、トラック車体タイプ(トラクタートレーラー、その他)、販売チャネル(OEM、その他)、および地域(北米、その他)によって分類されます。市場予測は、金額(米ドル)および数量(単位)で提供されます。

※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
本レポートは、ヘビーデューティトラック市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測を詳細に分析したものです。市場は、トン数タイプ(10~15トン、15トン超)、クラス(クラス7、クラス8)、推進タイプ(ディーゼル、バッテリー電気など)、用途(建設・鉱業など)、トラックボディタイプ(トラクター・トレーラーなど)、販売チャネル(OEMなど)、および地域(北米など)によってセグメント化されています。市場予測は、金額(米ドル)と台数(ユニット)の両方で提供されます。
1. 市場概要と予測
ヘビーデューティトラック市場は、2025年には2,325.7億米ドルと評価され、2030年までに3,012.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は5.31%です。この市場は、排出ガス規制の強化、前例のないインフラ投資、バッテリーおよび水素技術の急速な進歩によって大きく変化しています。フリート事業者は、短期的な排出ガス規制への対応と長期的な電動化計画の間で、購入決定を慎重に行っています。
市場の成長は、アジア太平洋地域が最も速く、かつ最大の市場として牽引しています。市場集中度は中程度であり、既存のメーカーが新しいプラットフォームに投資する一方で、ソフトウェア専門家やバッテリーサプライヤーがエコシステムに参入し、競争環境が激化しています。政策に関連する先行購入サイクルが短期的なディーゼル車の販売量を押し上げる一方で、コストパリティの達成が近づくにつれて、各地域の見通しにはゼロエミッション車への急速な転換が組み込まれています。アジア太平洋地域の規模の優位性、北米の政府調達インセンティブ、ヨーロッパの段階的な導入計画が相まって、一部の回廊における貨物輸送の軟化にもかかわらず、市場の成長見通しは堅調に推移しています。
2. 主要な市場トレンドと洞察
2.1. 促進要因
* Eコマース貨物量の拡大(CAGRへの影響: +1.2%): Eコマースの拡大は、ラストマイル配送の最適化と地域配送ネットワークの強化を通じて、ヘビーデューティトラックの需要を促進しています。オンライン小売の急増は、都市部での中型電気トラックの需要を生み出しており、ゼロエミッション規制がディーゼル車の運行をますます制限しています。
* 厳格なグローバル排出ガス規制によるフリート更新の促進(CAGRへの影響: +0.9%): 主要市場における規制枠組みは、フリートの電動化に前例のない圧力をかけています。米国環境保護庁(EPA)のフェーズ3基準では、2032年までに職業用車両の50%をゼロエミッションにするよう求めており、EUの改訂されたCO2基準は2040年までに排出量を90%削減することを義務付けています。
* インフラ刺激策(例: 米国IIJA、EUグリーンディール)(CAGRへの影響: +0.7%): 米国のインフラ投資雇用法(IIJA)は、交通インフラ改善に5,674億米ドルを割り当て、そのうち779億米ドルが貨物インフラ強化に特化しています。この投資は、建設および公共事業車両の直接的な需要を生み出すとともに、ヘビーデューティトラックフリートの運用コストを削減する道路状況を改善します。
* アジア太平洋地域における水素回廊パイロットプログラム(CAGRへの影響: +0.4%): 日本とインドは、ヘビーデューティ用途向けの水素インフラ開発を主導しています。これらのプログラムは、バッテリーの重量と充電時間の制限により水素がバッテリー電気ソリューションよりも実用的である長距離用途に対応しています。
* OTA対応TCO最適化(CAGRへの影響: +0.3%): フリートマネージャー向けのOTA(Over-The-Air)対応TCO(Total Cost of Ownership)最適化は、車両のソフトウェアを遠隔で更新し、パフォーマンスを向上させ、メンテナンスコストを削減することで、運用効率を高めます。
* 南米における鉱業部門の電動化コミットメント(CAGRへの影響: +0.2%): 南米の鉱業部門における電動化へのコミットメントは、特にチリやペルーなどの国々で、鉱山運搬車両の電動化を推進しています。
2.2. 抑制要因
* ゼロエミッションヘビーデューティトラックの高い初期費用(CAGRへの影響: -1.1%): ゼロエミッションのトラックは、ディーゼル車に比べて2~3倍高い取得コストがかかります。バッテリーパックのコストは車両価格の30~40%を占めており、リチウムイオン価格が下落しているにもかかわらず、主要なコスト要因となっています。
* ディーゼル価格の変動が購入サイクルに影響(CAGRへの影響: -0.6%): ディーゼル価格の変動は、フリートの車両更新計画に不確実性をもたらします。価格の変動は、フリートの調達決定に影響を与え、事業者は高価格期には購入を遅らせ、価格が下落すると購入を加速させるため、不規則な需要パターンが生じ、OEMの生産計画を複雑にしています。
* 半導体不足によるADAS/EV生産の遅延(CAGRへの影響: -0.4%): 半導体不足は、先進運転支援システム(ADAS)や電気自動車(EV)の生産を遅らせ、ヘビーデューティトラック市場に影響を与えています。
* EUの厳格な車軸重量規制による積載量経済性の制限(CAGRへの影響: -0.3%): EUの厳格な車軸重量規制は、車両の積載量を制限し、フリート事業者の経済性に影響を与えています。
3. セグメント別分析
* トン数タイプ別: 15トン超のセグメントが2024年に61.40%の市場シェアを占め、長距離貨物輸送や最大積載量を必要とする建設用途の優位性を反映しています。一方、10~15トンセグメントは、都市配送の最適化と中型電動化の採用によって牽引され、2030年までに9.50%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* クラス別: クラス8車両が2024年に70.80%の市場シェアを維持し、長距離貨物輸送や重建設用途における不可欠な役割を反映しています。しかし、クラス7トラックは、積載量と電動化経済性の最適な妥協点として、2030年までに8.30%のCAGRで最も強い成長軌道を示しています。
* 推進タイプ別: ディーゼル推進が2024年に83.90%の市場シェアを維持し、航続距離、給油速度、インフラの可用性における技術の継続的な運用上の利点を示しています。しかし、バッテリー電気システムは、運用サイクルが現在の技術能力と一致する場所での急速な採用により、2030年までに38.50%という驚異的なCAGR成長を達成すると予測されています。代替燃料(CNG、LNG、バイオディーゼルなど)も、特に中国で牽引力を増しています。
* 用途別: 貨物・物流アプリケーションが2024年に55.70%の市場シェアを占め、2030年までに11.69%のCAGRで成長すると予測されており、Eコマースの拡大とサプライチェーン最適化の取り組みによって牽引されています。地方自治体・公共事業は、予測可能なルート、集中型メンテナンス施設、公共部門の持続可能性義務により、最も高い電動化採用率を示しています。
* トラックボディタイプ別: トラクター・トレーラー構成が2024年に48.60%の市場シェアを占め、2030年までに10.90%のCAGRで成長すると予測されており、長距離貨物輸送および複合輸送業務における不可欠な役割を反映しています。
* 販売チャネル別: OEMおよび初回購入チャネルが2024年に74.10%の市場シェアを占め、2030年までに12.10%のCAGRで堅調に成長すると予測されており、フリート事業者が完全な保証と最新の技術機能を備えた新しい機器を好むことを示しています。
4. 地域別分析
* アジア太平洋: 2024年の世界収益の47.21%を占め、2030年までに9.30%のCAGRで拡大すると予測されており、中国の政策支援型電気トラックエコシステムに支えられています。インドの貨物回廊は政府の支援を受けており、日本は燃料電池システムをリードしています。
* 北米: 貨物集約型経済と確立されたクラス8文化によって牽引され、価値で第2位にランクされています。2027年に発効するEPAフェーズ3基準は、2025年から先行購入活動を促進し、ゼロエミッションモデルへの加速的な切り替えの前に一時的にディーゼル生産を増加させます。
*ヨーロッパ: 厳格な排出ガス規制と持続可能性への強いコミットメントにより、電気トラックの導入が加速しています。特に、都市部での配送や地域内輸送において、ゼロエミッション車両への移行が進んでおり、EUのグリーンディール政策がこれを後押ししています。ドイツ、フランス、オランダなどの国々が、充電インフラの整備と購入補助金を通じて市場を牽引しています。
* その他の地域: ラテンアメリカ、中東、アフリカが含まれ、これらの地域では経済成長とインフラ開発が商用車市場の需要を促進しています。特に、鉱業、農業、建設部門からの需要が堅調であり、今後数年間で着実な成長が見込まれています。
5. 競争環境
世界の電気トラック市場は、確立された自動車メーカーと新興のEV専門企業の両方からの激しい競争が特徴です。主要な市場プレーヤーには、Tesla、BYD、Daimler Truck AG、Volvo Group、PACCAR Inc.、Traton Group、Ford Motor Company、Rivian Automotive, Inc.、Nikola Corporation、Xos Trucksなどが含まれます。これらの企業は、製品革新、戦略的提携、地理的拡大、および充電インフラへの投資を通じて市場シェアを獲得しようと努めています。特に、バッテリー技術の進歩と充電時間の短縮は、競争優位性を確立するための重要な要素となっています。また、フリート事業者向けの包括的なソリューション(車両、充電、サービス)の提供も、市場での成功に不可欠です。
本レポートは、総車両重量26,000ポンドを超える新型のクラス7およびクラス8の大型トラック市場に焦点を当てています。これには貨物輸送、建設、自治体、その他の業務用車両が含まれますが、中古車、中型トラック、トレーラー、アフターマーケット部品は対象外です。
市場の成長を牽引する要因としては、Eコマース貨物量の増加、厳しい排出ガス規制(フリート更新を促進)、米国IIJAやEUグリーンディールなどのインフラ刺激策、アジア太平洋地域での水素回廊パイロットプログラム、OTA(Over-the-Air)によるフリート管理のTCO(総所有コスト)最適化、南米の鉱業部門における電化へのコミットメントが挙げられます。一方、市場の抑制要因としては、ゼロエミッション大型トラックの高い初期費用、ディーゼル価格の変動、ADAS/EV生産を遅らせる半導体不足、EUのより厳格な車軸重量規制による積載量経済性の制約があります。
市場規模と成長予測は、トン数(10~15トン、15トン超)、クラス(クラス7、クラス8)、推進タイプ(ディーゼル、バッテリー電気、燃料電池電気、代替燃料)、用途(建設・鉱業、貨物・物流、自治体・公益事業など)、トラックボディタイプ、販売チャネル、および地域(北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ)別に詳細に分析されています。
競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびDaimler Truck Holding AG、Traton SE、Volvo Group、PACCAR Inc.、Dongfeng Motor Corporation、Tata Motors Ltd、FAW Group Corp.、CNHTC (Sinotruk)、Ashok Leyland Ltd、Isuzu Motors Ltd.、Hino Motors Ltd.、Navistar International、Iveco Group N.V.、Hyundai Motor Co.、Nikola Corporation、JAC Motors、Kamaz PJSC、Foton Motor Co. Ltd.など主要企業のプロファイルが提供されています。
調査手法は厳格であり、フリート管理者、ディーラー、OEM製品戦略担当者、排出ガス規制専門家への一次調査、OICA、US Federal Highway Administration、Eurostat Comext、China’s MIITなどの信頼できる情報源からの二次調査が含まれます。市場規模の算出と予測は、GDP連動型貨物需要、公共事業支出、排出ガス基準、バッテリーコスト曲線、平均フリート年齢などの主要変数を考慮したトップダウンおよびボトムアップのアプローチを用いて行われています。データは毎年更新され、重要なイベント発生時には中間更新も実施されます。
本レポートの主要な知見として、大型トラック市場は2025年に2,325.7億米ドル規模であり、2030年までに年平均成長率(CAGR)5.31%で3,012.3億米ドルに達すると予測されています。推進技術別では、バッテリー電気トラックが2030年まで38.50%と最も高いCAGRで成長すると見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が世界の収益の47.21%を占め、2030年まで9.30%と最速のCAGRを記録すると予測されています。規制の影響も大きく、米国EPAフェーズ3基準やEUのCO₂排出量90%削減目標などの義務化により、フリートは通常のライフサイクルよりも早く車両を交換または改修せざるを得なくなり、規制主導の需要急増が生じています。
Mordor Intelligenceの市場価値予測(2025年で2,325.7億米ドル)は、他社の予測(3,245億米ドル、2,741.1億米ドル)と比較して、中型トラックの範囲、電気トラックの価格プレミアムの扱い、通貨換算のタイミング、政策変更後の予測更新頻度といった要因により差異が生じることが指摘されています。Mordor Intelligenceは、厳格な調査範囲の選定、変数の透明性、頻繁な更新サイクルにより、信頼性の高いベースラインを提供していると強調されています。
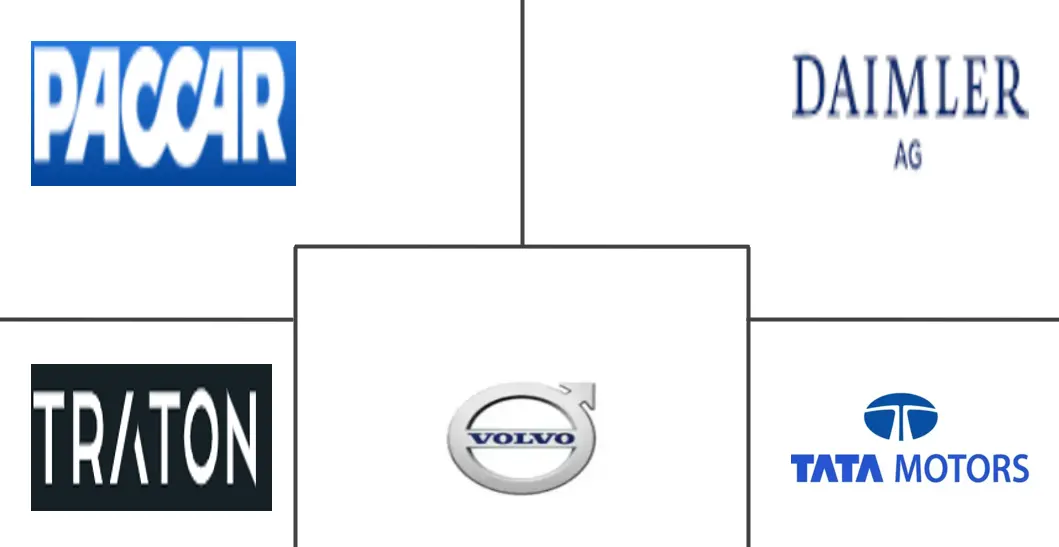

1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
-
4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 拡大するeコマース貨物量
- 4.2.2 厳格な世界的排出規制がフリート更新を推進
- 4.2.3 インフラ刺激策(例:米国IIJA、EUグリーンディール)
- 4.2.4 アジア太平洋地域における水素回廊パイロットプログラム
- 4.2.5 フリート管理者向けOTA対応TCO最適化
- 4.2.6 南米における鉱業部門の電化へのコミットメント
-
4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 ゼロエミッション大型トラックの高額な初期費用
- 4.3.2 購入サイクルに影響を与える不安定なディーゼル価格環境
- 4.3.3 ADAS/EV生産を遅らせる半導体不足
- 4.3.4 積載量経済性を制限するEUの厳格な車軸重量規制
- 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
-
4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(金額(米ドル)および数量(単位))
-
5.1 トン数タイプ別
- 5.1.1 10~15トン
- 5.1.2 15トン超
-
5.2 クラス別
- 5.2.1 クラス7
- 5.2.2 クラス8
-
5.3 推進タイプ別
- 5.3.1 ディーゼル
- 5.3.2 バッテリー電気
- 5.3.3 燃料電池電気 (FCEV)
- 5.3.4 代替燃料 (CNG、LNG、バイオディーゼル)
-
5.4 用途別
- 5.4.1 建設・鉱業
- 5.4.2 貨物・物流
- 5.4.3 市営・公益事業
- 5.4.4 その他
-
5.5 トラックボディタイプ別
- 5.5.1 トラクター・トレーラー
- 5.5.2 リジッドダンプ
- 5.5.3 タンカー
- 5.5.4 その他
-
5.6 販売チャネル別
- 5.6.1 OEM / 初回購入
- 5.6.2 リース・レンタル
- 5.6.3 アフターマーケット改造
-
5.7 地域別
- 5.7.1 北米
- 5.7.1.1 米国
- 5.7.1.2 カナダ
- 5.7.1.3 その他の北米
- 5.7.2 南米
- 5.7.2.1 ブラジル
- 5.7.2.2 アルゼンチン
- 5.7.2.3 その他の南米
- 5.7.3 欧州
- 5.7.3.1 ドイツ
- 5.7.3.2 英国
- 5.7.3.3 フランス
- 5.7.3.4 イタリア
- 5.7.3.5 ロシア
- 5.7.3.6 その他の欧州
- 5.7.4 アジア太平洋
- 5.7.4.1 中国
- 5.7.4.2 インド
- 5.7.4.3 日本
- 5.7.4.4 韓国
- 5.7.4.5 オーストラリア・ニュージーランド
- 5.7.4.6 その他のアジア太平洋
- 5.7.5 中東・アフリカ
- 5.7.5.1 サウジアラビア
- 5.7.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.7.5.3 エジプト
- 5.7.5.4 トルコ
- 5.7.5.5 南アフリカ
- 5.7.5.6 その他の中東・アフリカ
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動き
- 6.3 市場シェア分析
-
6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
- 6.4.1 ダイムラートラックホールディングAG
- 6.4.2 トラトンSE
- 6.4.3 ボルボグループ
- 6.4.4 パッカー社
- 6.4.5 東風汽車集団
- 6.4.6 タタ・モーターズ社
- 6.4.7 中国第一汽車集団
- 6.4.8 CNHTC (シノトラック)
- 6.4.9 アショック・レイランド社
- 6.4.10 いすゞ自動車株式会社
- 6.4.11 日野自動車株式会社
- 6.4.12 ナビスター・インターナショナル
- 6.4.13 イヴェコ・グループN.V.
- 6.4.14 現代自動車株式会社
- 6.4.15 ニコラ・コーポレーション
- 6.4.16 JACモーターズ
- 6.4.17 カマズPJSC
- 6.4.18 フォトンモーター株式会社
7. 市場機会と将来展望
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

大型トラックは、現代社会の物流を支える上で不可欠な存在であり、その定義、種類、用途、関連技術、市場背景、そして将来展望は多岐にわたります。まず、大型トラックの定義からご説明いたします。日本における大型トラックは、道路運送車両法などの法令に基づき、車両総重量が11トン以上、または最大積載量が6.5トン以上の貨物自動車を指すのが一般的です。運転には「大型自動車免許」が必要とされ、その高い積載能力と長距離輸送性能から、経済活動の動脈として極めて重要な役割を担っています。中型トラックや準中型トラックと比較して、より大量の貨物を一度に運搬できる点が最大の特徴であり、日本の産業と国民生活を根底から支える基盤となっています。
次に、大型トラックの種類についてご説明いたします。その用途に応じて多種多様なボディタイプが存在します。最も基本的なものは「平ボディ」と呼ばれる荷台がフラットなタイプで、様々な形状の貨物に対応できる汎用性があります。荷物を雨風から守る「バンボディ」は、一般貨物輸送に広く用いられ、特に温度管理が必要な食品や医薬品の輸送には「冷凍冷蔵車」が不可欠です。荷台の側面が翼のように開閉する「ウイングボディ」は、フォークリフトなどによる効率的な荷役作業を可能にし、物流現場での作業効率向上に貢献しています。土砂や砂利などのばら積み貨物を運搬する「ダンプカー」、液体やガスを輸送する「タンクローリー」、生コンクリートを運ぶ「ミキサー車」なども大型トラックの代表的な種類です。また、トレーラーを牽引する「トラクタ」も大型トラックの一種であり、連結することでさらに大量の貨物や特殊な形状の貨物を輸送できます。これらの車両は、軸数や駆動方式によっても細分化され、それぞれの用途に最適な設計が施されています。
大型トラックの用途は、日本のあらゆる産業分野に及びます。最も主要な用途は、製造業の製品、農産物、水産物、日用品などの長距離・中距離輸送を担う物流です。工場から倉庫へ、倉庫から小売店へと、サプライチェーンの各段階で大量の物資を効率的に移動させる役割を果たしています。建設現場では、土砂、砂利、セメント、鉄骨などの資材運搬にダンプカーやミキサー車、クレーン車などが活躍し、社会インフラの整備に貢献しています。また、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬にも大型トラックが用いられ、環境衛生の維持にも不可欠です。石油製品や化学薬品などの危険物輸送、あるいは大型機械や特殊部品といった特殊貨物の輸送にも、専用の大型トラックが用いられます。このように、大型トラックは私たちの日常生活を支えるあらゆる物資の移動を可能にし、経済活動の円滑な運営に欠かせない存在です。
これらの多様な用途を支えるのが、大型トラックに搭載される先進的な関連技術です。エンジンの分野では、高効率化と低排出ガス化が絶えず追求されており、最新の排ガス規制(日本のポスト新長期規制など)に対応したクリーンディーゼルエンジンが主流です。近年では、ハイブリッドシステムや電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)といった次世代パワートレインの開発も活発に進められています。安全技術の進化も目覚ましく、衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)、車線逸脱警報装置(LDWS)、アダプティブクルーズコントロール(ACC)などの先進運転支援システム(ADAS)が標準装備されつつあります。ドライバーの居眠りや脇見運転を検知するドライバーモニタリングシステム、車両周辺の死角を補うサラウンドビューモニターなども普及し、事故防止に大きく貢献しています。また、車両の運行状況をリアルタイムで管理するテレマティクスシステムやIoT技術は、燃費管理、運行ルート最適化、遠隔診断、予知保全などを可能にし、運行効率と安全性の向上に寄与しています。さらに、空気抵抗を低減する空力デザインや、高張力鋼板やアルミニウム合金などの軽量素材の採用により、積載量と燃費性能の両立が図られています。将来的には、自動運転技術の導入も期待されており、隊列走行(プラトーニング)の実証実験なども進められています。
大型トラックの市場背景は、需要と供給の両面で複雑な課題を抱えています。国内の主要メーカーとしては、日野自動車、いすゞ自動車、三菱ふそうトラック・バス、UDトラックスが挙げられ、それぞれが国内外で高い競争力を持っています。市場の需要は、eコマースの拡大や経済活動の活発化に伴い堅調に推移していますが、供給側には深刻な課題が存在します。最も喫緊の課題は「ドライバー不足」です。高齢化の進行、若年層のトラックドライバー離れ、長時間労働や厳しい労働環境が原因で、慢性的な人手不足が続いています。これに加え、2024年4月からはトラックドライバーの時間外労働に上限規制が適用される「2024年問題」が控えており、物流能力の低下や運賃上昇、ひいては経済全体への影響が懸念されています。また、地球温暖化対策として、より厳しい環境規制が導入され、車両の電動化や燃料効率の向上が強く求められています。燃料価格の変動も運行コストに大きな影響を与え、運送会社の経営を圧迫する要因となっています。これらの課題に対し、業界全体で効率化、省力化、そして持続可能性を追求する動きが加速しています。
将来展望として、大型トラック業界は大きな変革期を迎えることが予想されます。最も注目されるのは「脱炭素化」への動きです。ディーゼルエンジンからの脱却を目指し、電気トラック(EVトラック)や燃料電池トラック(FCVトラック)の開発・普及が加速するでしょう。これに伴い、充電インフラや水素ステーションの整備が喫緊の課題となります。また、合成燃料やバイオ燃料といった代替燃料の実用化も期待されています。次に、「自動運転技術」の進化と導入です。ドライバー不足の解消と安全性向上、運行効率の最大化を目指し、高速道路での隊列走行や、特定の区間での完全自動運転(レベル4)の実用化が進むと考えられます。これにより、ドライバーはより付加価値の高い業務に集中できるようになるでしょう。さらに、「デジタル化」の推進も不可欠です。AIを活用した物流最適化システム、予知保全を可能にする高度なテレマティクス、ブロックチェーン技術を用いたサプライチェーンの透明化などが進展し、より効率的でレジリエントな物流システムが構築されるでしょう。ドライバーの労働環境改善も重要なテーマであり、キャビンの快適性向上、疲労軽減技術の導入、そして労働時間の適正化が図られることで、ドライバーの確保と定着に繋がると期待されます。大型トラックは、これからも社会の基盤を支え続けるために、技術革新と制度改革を重ねながら、持続可能な物流の実現に向けて進化し続けることでしょう。